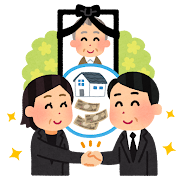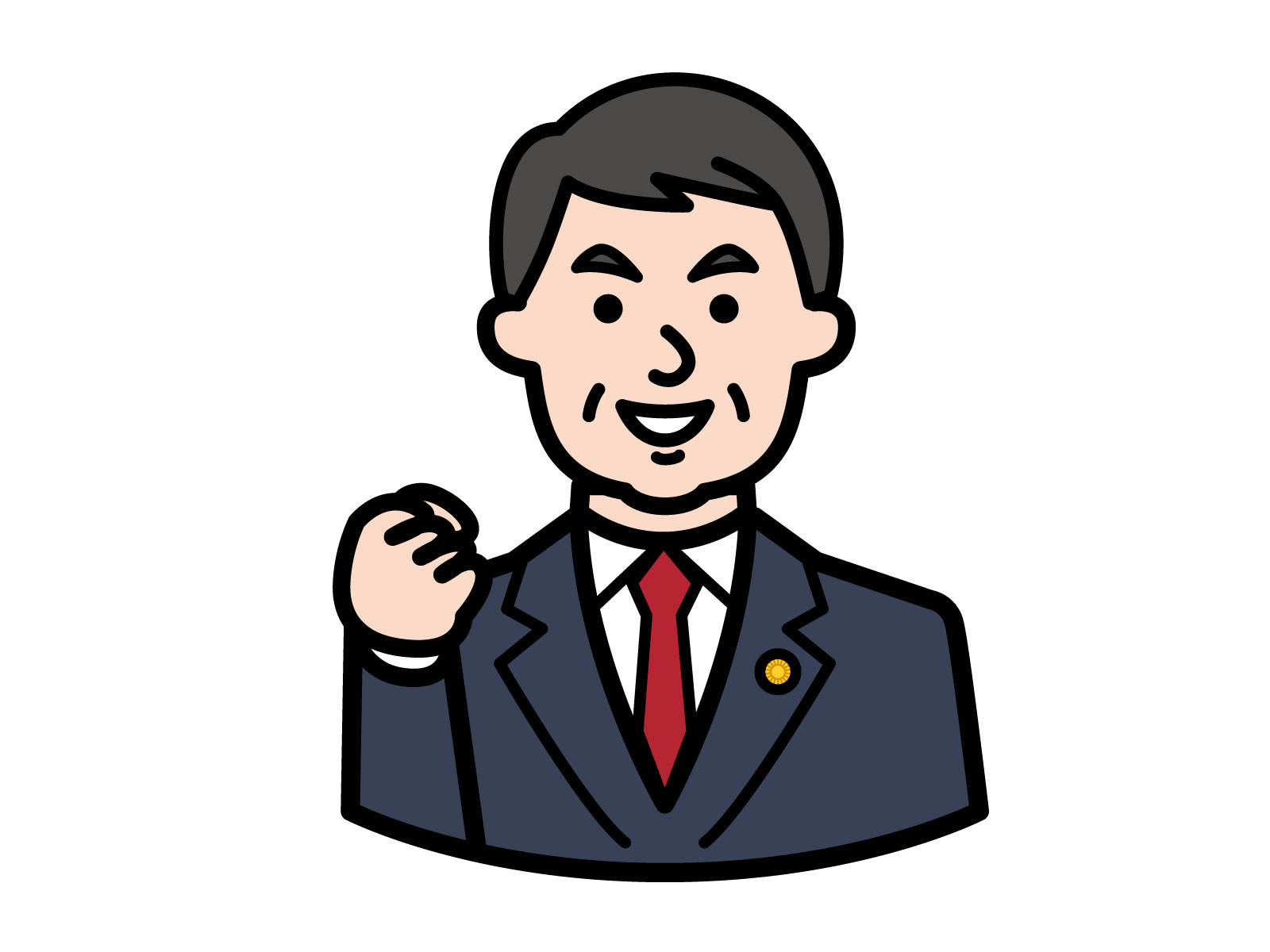無効な遺言書を死因贈与契約として有効にしたい。
無効な遺言書を、有効にしたい!
無効な遺言書を実質的に有効にできないか。できるとしてその要件は何かを、約20年にわたり岐阜県内の相続問題(遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言書など)を解決してきた弁護士杉島健二が、わかりやすく解説します。
問題の所在 ー 遺言書が無効になってしまった!
一般に、遺言書はその法律上の成立要件が厳しく、実際にも、要件を欠くとして無効なってしまう遺言が生じることがあります。
これでは、遺言者の意思に反したり、自分に有利な遺言書を書いてもらった人は困ってしまいます。
そこで、無効となってしまった遺言書について、実質的には有効とする方法がないかが、問題となります。
死因贈与と、その成立要件は?
無効な遺言書を実質的に有効にするには死因贈与契約が成立しないかを検討する。
ア 死因贈与契約とは
無効となってしまった遺言書を実質的に有効にするための方策として、従来か考えられてきたのが、遺言者(ここでは、「A」とします。)とその遺言書により財産をもらう人(ここでは、「B」とします。)との間に死因贈与契約が成立しないかが検討されてきました。
死因贈与契約とは、特定の財産を持つAが、その特定の財産を自分が死んだときに、Bに贈与する(無償で上げる。)契約を言います。
Aが死んだときに自分の物をBに移転させるという遺言書とほぼ同じ効果をもたらすので、無効な遺言書について死因贈与が成立しないかが検討されてきたのでした。
イ 死因贈与契約の成立要件
死因贈与も、契約の一つですから、二当事者間の意思表示の合致によって成立します。
つまり、死んだら特定の物をあげようとするAの死因贈与契約の申し込みの意思表示と、それをもらおうとする死因贈与契約の承諾の意思表示が必要です。
この点が、特定の財産をだれかに帰属させようとする単独行為である遺言とことなります。
では、どのような場合に、こうした申し込みの意思表示と承諾の意思表示があったと認定できるかが問題となりますが、
① Aがどのような意図で遺言書を作成したのかなどの遺言書作成の経緯
② Bの遺言書とのかかわり
③ その他の事情
を総合判断して、申し込みの意思表示と承諾の意思表示を認定していくことになると考えられます。
裁判例の検討
では、実際の裁判例では、どのような判断がされているか見てみましょう。
1 死因贈与の成立を認めた裁判例
① 広島高等裁判所平成15年7月9日判決
ア 事案
死期を悟った遺言者Aが,Bに依頼してBに遺言書を作成し、それにAが署名押印した遺言書が無効とされ、死因贈与契約の成立が争われた事案。
イ 判旨
ところで、死因贈与は、遺贈と同様に死亡が効力発生要件とされているため、遺贈に関する規定が準用されるが(民法554条)、死因贈与の方式については遺贈に関する規定の準用はないものと解される(最判昭和32年5月21日民集11巻5号732頁参照)。したがって、遺言書が方式違背により遺言としては無効な場合でも、死因贈与の意思表示の趣旨を含むと認められるときは、無効行為の転換として死因贈与の意思表示があったものと認められ、相手方のこれに対する承諾の事実が認められるときは、死因贈与の成立が肯定されると解せられる。
これを本件についてみると、前記認定のとおり、亡Aは、死期が迫っていることを悟り、死後自己所有の財産を、敢えて養子である原審原告を除外して、実子である原審被告らに取得させようと考え、本件遺言書を作成したのであり、その目的は、専ら、死亡時に所有財産を原審被告らに取得させるという点にあったこと、遺言という形式によったのは、法的知識に乏しい亡Aが遺言による方法しか思い付かなかったからであり、その形式にこだわる理由はなかったこと、そのため結局遺言としては無効な書面を作成するに至ったこと、亡はA、本件遺言書の作成当日、Bを介し、受贈者である原審被告らにその内容を開示していること等の点にかんがみれば、本件遺言書は死因贈与の意思表示を含むものと認めるのが相当である。
そして、前記認定のとおり、原審被告Cは、本件遺言書作成には立ち会ってはいなかったものの、その直後に亡Aの面前でその内容を読み聞かされ、これを了解して本件遺言書に署名をしたのであるから、このときに亡Aと原審被告Cとの間の死因贈与契約が成立したといえる。また、原審被告Dは、本件遺言書に署名することはなかったものの、本件遺言書作成日に、病院内で、Bから本件遺言書の内容の説明を受け、これに異議はない旨述べた上、亡Aを見舞い、その際にも本件遺言書の内容に異議を述べることもしなかったのであるから、亡Aに対し、贈与を受けることを少なくとも黙示に承諾したものというべきであり、このときに、亡Aと原審被告Dとの間の死因贈与契約が成立したといえる。
以上によれば、原審被告ら主張の平成11年1月17日付死因贈与契約の成立が認められる。
ウ ポイント
判旨は、まず一般論として、「遺言書が方式違背により遺言としては無効な場合でも、死因贈与の意思表示の趣旨を含むと認められるときは、無効行為の転換として死因贈与の意思表示があったものと認められ」る場合には、死因贈与の申し込みの意思表示があったとするとしています。
また、「相手方のこれに対する承諾の事実が認められるときは、死因贈与の成立が肯定されると解せられる。」として、相手方の承諾の意思表示があれば、死因贈与の契約が成立するとしています。
これを前提に、「亡Aは、死期が迫っていることを悟り、死後自己所有の財産を、敢えて養子である原審原告を除外して、実子である原審被告らに取得させようと考え、本件遺言書を作成した」こと、そしてその目的は、①「専ら、死亡時に所有財産を原審被告らに取得させるという点にあったこと」、②「遺言という形式によったのは、法的知識に乏しい亡Aが遺言による方法しか思い付かなかったからであり、その形式にこだわる理由はなかったこと」、③「そのため結局遺言としては無効な書面を作成するに至ったこと」、④「亡はA、本件遺言書の作成当日、Bを介し、受贈者である原審被告らにその内容を開示していること」に鑑みれば、本件遺言書は死因贈与契約の申し込みの意思表示にあたるとしています。
そして、「原審被告Cは、本件遺言書作成には立ち会ってはいなかったものの、その直後に亡Aの面前でその内容を読み聞かされ、これを了解して本件遺言書に署名をした」ので、原審被告Cには死因贈与契約の承諾の意思表示があり、このときに亡Aと原審被告Cとの間の死因贈与契約が成立したとしています。
また、「原審被告Dは、本件遺言書に署名することはなかったものの、本件遺言書作成日に、病院内で、Bから本件遺言書の内容の説明を受け、これに異議はない旨述べた上、亡Aを見舞い、その際にも本件遺言書の内容に異議を述べることもしなかったのであるから」として、亡Aに対し、贈与を受けることを少なくとも黙示に承諾することにより承諾の意思表示があったとして、このときに、亡Aと原審被告Dとの間の死因贈与契約が成立したとしています。
このように判旨は、死因贈与契約の申し込みの意思表示の存在については、遺言書作成の経緯や目的、また、相手方(本件で言えば反訴被告C、反訴被告D)に示していたかどうかなどを総合判断しています。
他方、相手方による死因贈与契約の承諾の意思表示の存在については、相手方が、遺言書にどのようにかかわったかなどの事情を総合判断しています。
そして、承諾の意思表示があったときに、死因贈与契約が成立したと判断していると言えるでしょう。
② 東京地方裁判所高等裁判所昭和56年8月3日判決
ア 事案
判読しづらい記載、及び、誤記のある記載がる自筆遺言証書が様式性を欠く無効な場合に、死因贈与契約を認定できるか。
イ 判旨
これに本件遺言書が作用されるに至つた経緯について既に認定した事実を加えて判断すれば、仮に本件遺言書が自筆証書遺言としての要式性を欠くものとして無効であるとしても、Aが、昭和五一年三月一七日、自分が死亡した場合には自分の財産の二分の一をBに贈与する意思を表示したものであり、原告はこの申し出を受け入れたものであると認めるのが相当である。
ウ ポイント
詳細な認定はないものの、やはり、死因贈与契約の申し込みの意思表示と承諾の意思表示を問題にしています。
③ 広島家庭裁判所昭和62年3月28日審判
ア 事案
作成日付の記載と押印のない自筆証書遺言としては無効な遺言書を死因贈与契約を称する書面と認めた事案。
イ 審判
(イ) 申立人Aが検認を受けた前記遺言書と題する文書は、その作成日付の記載がなく、作成者である、亡B(Aの夫)の押印もないから、自筆証書遺言としての要件を欠くもので、遺言としての法的効力を有するものとは認めることができない。従つて、遺言が有効であることを前提とする遺言執行者選任の申立は理由がない。
(ロ) しかし、前記遺言書と題する文書は、遺言としての法的効力はないとしても、前記認定事実に徴すると死因贈与契約の成立を証明する文書であることは明らかであると認められる。即ち、亡BとAとの問に、昭和51年7月下旬ころ、亡Bの所有する一切の財産を申立人に死因贈与する旨の契約が成立したことが明らかである。そして、死因贈与については、遺贈に関する規定が準用される(民法554条)。従つて、遺贈の執行に関する規定である民法1010条を準用して、死因贈与の執行のために執行者を選任することができるものと解される。
(ハ) Aとしては、亡Bが別紙遺言書と題する書面によつて表示している意思を実現することを希求しているのであるから、遺言執行者選任の申立が理由がないのであれば、次善の方法として死因贈与の執行者選任の申立。意思を当然に有するものと考えられるので、主文のとおりの審判をしても申立の趣旨をこえることにはならないものと解される。
(ニ) Aが、執行候補者として指示した前記吉原俊昌については、不適格事由は存しないから、同人を執行者に選任するのが相当である。よつて主文のとおり審判する。
ウ ポイント
死因贈与契約に関する亡Bによる申し込みの意思表示と、妻Aの承諾の意思表示が、どのような具体的な事実をもとに認定されたかについては、審判書の記載からは不明であり、何らかの準則を見出すことはできない。
また、蛇足であるが、広島家庭裁判所が、新贈与契約の成立を認めたのは、亡BのA以外の他の相続人が死因贈与契約の成立に反対しなかったという事情があったという点が大きいと考えられる。
審判書は、「申立人も前記文書が遺言としての効力を有することには疑問をもち,他の相続人に対し,協議によつて遺産の処理をして貰うべく協議をするよう申し込んだが他の相続人は,亡井田勝三の遺産を取得したいと考える人はなく,協議をするまでもなく申立人の一存で処理したらよいとして,協議に応じなかつた。このため申立人はやむなく本件申立に及んだ。」と記載しており、死因贈与契約の成立に反対する相続人がいないのであれば、成立を阻害する要素はないということになるからである。
④ 東京高等裁判所昭和60年6月26日判決
ア 事案
承認の一人に結核事由がるとして無効とされた公正証書遺言書が、書面による死因贈与として有効とならないか。
イ 判旨
民法550条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が軽率に贈与を行うことを予防するとともに贈与の意思を明確にし後日紛争が生じることを避けるためであるから、贈与が書面によってされたものといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によってされたこと、又は、書面が贈与の直接当事者において作成され、これに贈与その他の類似の文言が記載されていることは、必ずしも必要でなく、当事者の関与又は了解のもとに作成された書面において贈与のあったことを確実に看取しうる程度の記載がされていれば足りるものと解すべきところ、前記遺言公正証書は、Aの嘱託に基づいて公証人が作成したものであり、右公正証書には前記死因贈与の意思表示自体は記載されておらず、また、これを死因贈与の当事者間において作成された文書ということもできないが、前記認定のように、Aが本件土地を控訴人に死因贈与し、Aは右死因附与の事実を明確にしておくため公正証書を作成することとし、控訴人の了解の下に前記遺言公正証書の作成を嘱託したことが認められ、このことと遺贈と死因贈与とはいずれも贈与者の死亡により受贈者に対する贈与の効力を生じさせることを目的とする意思表示である点において実質的には変わりがないことにかんがみると、前記遺言公正証書は前記死因贈与について作成されたものであり、前記のようなかしの存在により公正証書としての効力は有しないものの、右死因贈与について民法550条所定の書面としての効果を否定することはできないものというべきである。
したがって、本件死因贈与は書面によるものというべきであり、これを取り消すことは許されない。
ウ ポイント
この判決は、遺言者の遺言書作成の意図や、無効な遺言証書作成前に、死因贈与契約の申し込みの意思表示と少額の意思表示があるからこの時点で死因贈与契約が成立していて、これを明確にするために公正証書遺言書が作成されたものであるとして、死因贈与契約の成立を認めました。
やはり、遺言その作成意図や作成経緯などが重視されています。
⑤ 水戸家庭裁判所昭和53年12月22日審判
ア 事案
押印を欠くため無効な自筆遺言証書が死因贈与として有効とならないか。
イ 判旨
しかしながら、右遺言書なる書面の内容自体から判断すれば、申立人に対し遣言者たる亡Aが自己の死亡を原因としてその財産及び会社の権利を贈与する意思を表示したいわゆる死因贈与の申込みと解され、而して申立人B尋問の結果によれば、右書面には亡Aの押印こそないが、全文及び日附署名は同人の自筆によるものであること、及び右死因贈与の申込みに対し当時これを申立人Bにおいて受諾したことが一応認められるから、右死因贈与契約は当時成立したものということができる。
ウ ポイント
これは、判決ではなく審判なので、詳細な事実認定はされていないものの、当該遺言書の書面の内容から判断して、亡Aによる死因贈与の申し込みの意思表示であると結論付け、また申立人Bにおいて受諾の意思表示があったと判断しています。
いずれにせよ、やはり、死因贈与の申し込みの意思表示と承諾の意思表示があったかどうかを重要視しています。
2 死因贈与の成立を否定した裁判例
① 大阪高等裁判所昭和43年12月11日判決
ア 事案
民法974条に違反し無効である公正証書遺言に関連して、死因贈与契約の成立が争われた事案。
イ 判旨
被控訴人Aが本件各物件を訴外亡Bから遺贈されたのを知ったのは、同訴外人の死後本件遺贈公正証書があることをCから知らされた時がはじめてのことであって、同訴外人Bの生前には同訴外人Bから被控訴人Aに本件各物件等を贈与または死因贈与する旨の直接または間接の意思表示があったことはなく、まして被控訴人Aが同訴外人Bに対して贈与または死因贈与を受諾する意思表示などをしたことはもとよりなかったことが認められ(るとして死因贈与契約の成立を否定した。)、
ウ ポイント
Aが、本件遺贈公正証書の存在を知ったのは、Bの死亡後であるから、Aによる生前のBに対する死因贈与契約の承諾の意思表示がない、としている点が最大のポイントである。承諾の意思表示は、生前のBに対して行う必要があり、死亡したBとの間ではもはや何の契約も成立しないからである。
② 仙台地方裁判所平成4年3月26日判決
ア 事案
他人が代筆した無効な自筆証書遺言に関連して、死因贈与契約が成立するか。
イ 判旨
証人B、同C(一部)の各証言並びに被告Dの本人尋問の結果によれば、訴外Eは、代筆した後、訴外Aが死亡してその葬儀の日まで本件書面を保管したうえ、葬儀の日にE方に持参して、Eや原告に対しこれを呈示したことが認められ、したがって、原告は葬儀の日以前に本件書面を見る機会はなかったのであるから、原告本人尋問の結果のうち、原告が訴外Bから本件書面を示されて死因贈与を承諾したという部分は、真実に反するものといわざるを得ない
ウ ポイント
原告が、亡Aの本件遺言書を見たのは、亡Aの死亡後であることをとらえて、原告には死因贈与契約の承諾の意思表示はないとして、死因贈与契約の成立を否定した。
原告の死因贈与契約の承諾の意思表示は、亡Aの生前になすべきものであって、原告が本件死因贈与契約書を見たのは、亡Aの死後であるから、生前のAに対する承諾の意思表示をする余地がなかったと言える。
死因贈与契約成立判断のポイント
以上のように、裁判例などは、死因贈与契約が成立するためには、死因贈与契約の申し込みの意思表示と承諾の意思表示が必要としています。
そして、これらの意思表示があったかどうかについては、贈与者の遺言書作成の意図や経緯、被贈与者の遺言書や贈与者とのかかわり方に関する諸事情を考慮していると言えます。
相続問題のお問い合わせ

弁護士杉島健二は、弁護士活動19年目。相続問題ならすぎしま法律事務所におまかせください。
感情が絡みやすい相続問題を冷静かつ法的に解決し、依頼者の権利を守ります。
ご相談の流れ
まずはお問い合わせフォームやLINEからお気軽にお問い合わせください。ご相談内容を確認しまして、初回無料相談(交通事故・相続)の日程を調整させていただきます。
メールでお問い合わせを頂いた場合は、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。
メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。
事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。お悩みや状況を詳しくお聞きした上で、解決の方向性や必要な手続きをご提案します。初回の相談料は無料ですので、安心してご利用ください。
必要なもの
関係する書類全部
ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。契約内容や費用についても事前に明確にご説明いたしますので、安心してお任せいただけます。
契約後は、迅速かつ丁寧に調査を行い、必要に応じて相手方との交渉や調停、裁判手続きを進めます。依頼者様の利益を最大限守るため、最善を尽くします。