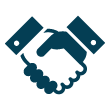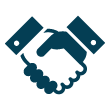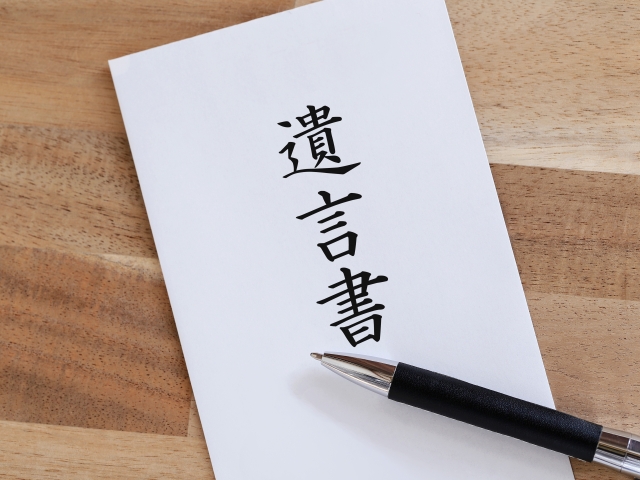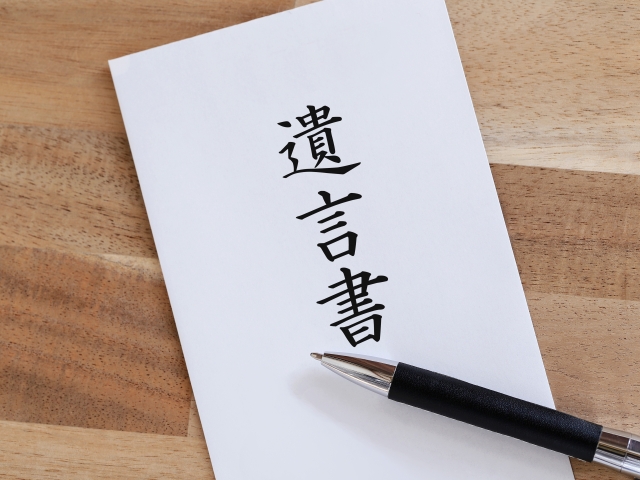岐阜で相続問題のご相談なら
相続問題の実績が豊富な
「すぎしま法律事務所」へご相談
相続問題の実績豊富な
すぎしま法律事務所へ
相続問題(遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄)は、岐阜の弁護士杉島健二へ
岐阜の相続問題の解決なら、すぎしま法律事務所(弁護士杉島健二)へ
相続問題なら、すぎしま法律事務所におまかせください。
感情が絡みやすい相続問題を冷静かつ法的に解決し、依頼者の権利を守ります。
相続問題で、すぎしま法律事務所が選ばれる理由
代表弁護士が担当
受任した弁護士(代表 杉島)が責任をもって処理いたします。
柔軟な対応
弁護士費用特約や分割払い、後払いなどのご相談も可能です。
岐阜エリア密着
弁護士一人の小さな事務所ですが、岐阜県・岐阜市に密着、地域の皆様のために活動しています。
すぎしま法律事務所では、岐阜県内の遺産分割、遺留分減額請求、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目 指します。
相続(遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成、相続放棄など)のこんなお悩みを解決します
遺産分割
遺言書を残さないまま親が亡くなり、兄弟間でトラブルになった。兄が勝手に遺産を管理し、遺産を分配してくれない。
遺留分侵害額請求
親が亡くなって遺言書が出てきたが、自分の取り分がすくない。納得がいかない。
遺言書作成
自分が死んだ後に、子どもたちが相続争いでもめてほしくない。
2人兄弟の息子がいるが、長男が障害者なので、長男に少しでも多く遺産を残したい。
相続放棄
親が亡くなったが、たくさんの借金がありそうだから放棄したい。
会ったこともない叔父にあたる人が亡くなって、叔父にお金を貸したという人からお金の支払いを請求された。
サポート内容
遺産分割
遺産分割とは?
遺産分割とは、相続が発生した際に、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人間で分ける手続きのことです。 遺産には不動産、預貯金、株式などさまざまな種類があり、相続人
全員で話し合い(遺産分割協議)を行い分配方法を決めます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判をすることになります。
サポート概要
遺産分割に関する法的なアドバイスや調整を行い、相続人間の対立を防ぎつつ、公正な分割を実現するお手伝いをします。
・遺産の調査と評価
・遺産分割協議のサポート
・調停や訴訟の代理
・専門的アドバイス
遺産分割のよくあるトラブル
- 誰が親の面倒を見たか?などの理由で、遺産の取り分についてお互いの主張が異なりトラブルに。
- 兄弟のうちの誰かが遺産を管理し、それを他の相続人に報告・分配してくれない。
- 生前に受けた贈与や、特別な貢献が遺産分割にどう反映されるかで意見が分かれるトラブル。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、相続人が最低限保障される相続財産の取り分を指します。被相続人が遺言や生前贈与で財産を特定の人に偏らせた場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで取り戻す権利があります。
サポート概要
遺留分を侵害された相続人の代理人として交渉や法的手続きを行い、公正な取り分を確保
するサポートを行います。
・遺留分侵害の確認
・交渉による解決
・調停や訴訟への対応
・書類作成と法的サポート
遺留分侵害額請求のよくあるトラブル
- 生前贈与の金額や時期を巡って証拠の提出が求められた。
- 親族間で感情的な対立が深まり、話し合いが進まない。
- 「自分だけが不当に扱われている」と感じることで争いがエスカレートする。
弁護士からのアドバイス
- 親が自分に不利な遺言書を書かれた場合でも、遺留分は法律上の正当な権利ですから、遺留分侵害額請求を行使することをためらう必要はありません。
- また、他の兄弟の意向に従って、あなたに不利な遺言書が作成された場合もあります。
遺言書作成
遺言書作成とは
遺言書作成とは、自分の財産を誰にどのように相続させるかを明確にするために、法的に有効な形で遺言書を作ることです。適切な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、自分の意思を確実に実現できます。
サポート概要
弁護士が依頼者の意思に基づいて、相続に関する財産の分け方や特定の人への遺贈などを法的に有効な形で記載した遺言書を作成いたします。法律に基づいて内容をアドバイスし、遺言書の作成や保管、必要に応じた執行までをお手伝いします。
・遺言内容の相談とヒアリング
・遺言書の作成サポート
・遺言書の保管と管理
・遺言執行者の指名と支援
・遺言書の定期的な見直し
遺言書作成のよくあるトラブル
- 法律で定められた形式を守っていないため、遺言書が無効とされた。
- 遺言書の内容が不明確で解釈が分かれて揉め事に。
- 遺言内容に不満を持つ相続人が遺留分を主張してきた。
- 遺言書が見つからずトラブルが長期化。
- 遺言書の記載が現実的ではなく、分割や処理が複雑化。
- 特定の相続人への偏りが原因で家族間の関係が悪化。
- 遺言書の存在自体が相続人にとって予想外で混乱。
相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、借金などの負債も含めた相続権を全て放棄する手続きです。
これにより、財産や債務を一切引き継がなくなります。
家庭裁判所に申立てを行い、法的に認められることで初めて成立します。
サポート概要
相続人が確実かつスムーズに相続放棄できるようさまざまな支援を行います。弁護士がサポートすることで、相続放棄の手続きが正確かつスムーズに進むだけでなく、相続放棄に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
・相続放棄の可否の確認
・家庭裁判所への申立て手続き
・放棄後の手続きサポート
・特殊なケースの対応
相続放棄のよくあるトラブル
- 相続放棄後に、債務者や債権者に対して財産を処分してしまい、放棄が無効になる。
- 3か月の熟慮期間を過ぎてしまい、相続放棄が認められない。
- 順位相続人が知らない間に放棄が行われ、混乱が生じる。
- 財産だけを相続したと思いきや、後から多額の借金が発覚する。
- 一部の相続人だけが放棄を選択し、残った相続人とのトラブルが発生する。
- 二次相続や連鎖相続により、複数の被相続人に対する手続きが絡み合い、混乱する。
弁護士からのアドバイス
- 相続放棄には、必ず家庭裁判所への申し立てが必要です。単に、他の相続人に、「放棄する」、「要らない」というだけでは相続放棄したことにはなりません。
- 被相続人が死亡してから3か月以上経った場合でも、事情によっては、相続放棄できる場合もあります。あきらめずに、弁護士に相談してください。
主な解決事例
相続問題のQ&A
相続一般に関するQ&A
相続とは、どのような制度ですか?
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の権利義務関係(法的地位)を、その人と一定の身分関係のある人に承継させて存続させる制度です。
例えば、妻と長男がいる夫・父が死亡して、その夫・父について相続が発生した場合に、その妻や長男が父の権利義務関係を取得します。
相続によって取得する権利義務関係は、不動産や預貯金といったプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
相続人には、誰がなるのですか?
被相続人が死亡し、相続が発生した場合、具体的にだれが相続人となるかは、民法の規定によってきめられています。
まず、配偶者、つまり被相続人である夫の妻、あるいは、被相続人である妻の夫は常に相続人となります。
次に、一定の血族も相続人になる場合があります。
配偶者以外の第一順位の相続人は、直系卑属です。直系卑属のうち、子がいれば子が相続人、子がいなくて孫がいる場合は孫が相続人、子も孫もいなくてひ孫がいる場合はひ孫が相続人となります。
第二順位は、直系尊属です。直系尊属のうち、父母、または、父もしくは母がいればそれらの者が相続人、父母がいなければ、祖父母、または、祖父もし
第三順位は、兄弟姉妹、または、甥姪です。すなわち、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人、兄弟姉妹がいない場合は甥や姪が相続人となります。
具体的な相続分は、どのような割合ですか?
まず、子と配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1ずつです。なお、子が数人いる場合は、2分の1をさらに人数で割った分が相続分です。
次に、配偶者と直系尊属人が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。なお、直系尊属が数人いる場合は、3分の1をさらに人数で割った分が相続分です。
最後に、配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の1で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。なお、兄弟姉妹が数人いる場合は、4分の1をさらに人数で割った分が相続分です。
相続放棄に関するQ&A
相続したくないときには、どうすればよいですか?
相続は、相続人となる人の意思や希望とは関係なく、被相続人の死亡という事実により発生します。
ところが、被相続人に膨大な借金がある場合などは、相続人は相続したくないと思うことがしばしばあります。
そこで、相続人の意思により、相続人の地位を放棄することや、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を相続することが認められる必要があります。前者のための制度が相続放棄で、後者のための制度が限定承認です。
相続放棄とは、どのような制度ですか?
相続放棄とは、相続人となった者が、家庭裁判所へ申述することにより、相続人としての地位、すなわち、被相続人から承継する権利義務関係を放棄することを言います。
相続放棄は、どのように行えばよいですか?
相続放棄は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する方法で行わなければなりません。自分が「放棄する」というだけでは、法的に相続放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。
但し、3カ月を経過した場合であっても、家庭裁判所に受理されるときがありますので、そのような場合には、必ず弁護士にご相談ください。
相続放棄できない場合は、ありますか?
相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときなど単純承認したとみなされる場合は、相続放棄ができなくなる時があります。
但し、そのような場合にも相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されるときがあるので、そのような場合には、弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続を、すぎしま法律事務所に依頼する場合のメリットは何ですか? 費用はいくらですか?
すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、岐阜の相続人の方の相続放棄を数多く担当してきました。
相続放棄の手続を、当事務所にご依頼していただいた場合、家庭裁判所に対して相続放棄申述の手続をするほか、判明している債権者に相続放棄をしたことを連絡します。この連絡により、被相続人の債権者が、相続人の方に請求することを防ぐことができ、煩わしさや不安から解放されます。
当事務所の相続放棄の費用は、一人当たり税込み5万5000円から11万円の範囲です。相続放棄する方が複数いらっしゃる場合は、適宜減額することがあります。弁護士費用以外の費用としては、裁判所に納める収入印紙800円(相続放棄する人一人当たり)、その他戸籍などの取り寄せ費用、郵便代などです。
遺産分割に関するQ&A
遺産分割とは何ですか?
遺産分割とは、相続人全員で、被相続人の遺産を分割、すなわち、遺産のうち具体的に何をどの相続人が取得するかを決めることを言います。
遺産分割は、通常、被相続人の遺言書がない場合に行われますが、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意のもとに遺産分割をすることができます。
遺産分割をした後は、その後の法務局や金融機関で手続きをしたりするためや、遺産分割が成立したことの証拠とするために、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割をする際には、何をどう進めていけばよいですか?
遺産分割をするにあたっては、通常、以下の問題を検討、解決していくべきとされています。
① 相続人の範囲を確定する。
そもそも、具体的にだれが相続人なのかを確定する必要があります。
② 遺言書の有無、効力などを確認する。
有効な遺言書があるかないかによって、遺産分割すべき範囲が違ってきたり、原則として遺産分割できない場合もありますので、この点が確認されます。
③ 遺産の範囲と価格
遺産分割の対象となる遺産の範囲とその価格を確定します。被相続人の遺産とは、相続発生時に被相続人に所属していた財産となります。
これ以外の財産は、遺産に含まれないので、原則として、遺産分割の対象になりません。
④ 遺産の具体的な分割
遺産のうち、どの財産をどの相続人が分けるかを決めます。
⑤ 遺産分割協議書の作成
後に、遺産分割の内容を証明したり、法務局や金融機関で名義変更の手続きなどをするために遺産分割協議書を作成します。
相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、どうすればいいですか?
まず、弁護士に依頼していただいて、弁護士が他の相続人連絡交渉することによって、遺産分割がまとまる場合があります。
弁護士が介入しても遺産分割がまとまらない場合には、調停や審判など家庭裁判所の手続を利用することにより解決します。
遺留分に関するQ&A
遺留分とは、何ですか?
遺留分とは、わかりやすく言うと、一定の相続人が、被相続人(亡くなられた親族の方)の遺産から、被相続人の遺言書の内容にかかわらず、一定の遺産を受け取ることができる権利のことを言います。
遺言書は被相続人が自由にその内容を作成できます。他方、相続には、遺産に対する相続人の潜在的持分という性質や、相続人の生活保障という性質があるので、これらの点を保護するのが遺留分の趣旨です。
誰が、遺留分を請求できますか?
遺留分を請求できる者(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はない点に注意が必要です。
遺留分の具体的な割合は、どのようなものですか?
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これらの割合は、相続人全員分の割合ですから、各相続人の具体的な遺留分は、これらの割合に法定相続分をかけた割合となります。
遺留分は、どのように行使すればよいですか?
行使の方法については制限がなく、裁判上行使してもよいし、裁判外でも行使してもよいです。ただし、裁判外で行使する場合は、行使したかどうかという点や、期間制限との関係でいつ行使したかという点が、後日問題とならないように配達証明付きの内容証明郵便で行使することが望ましいです。
遺留分はいつまでに行使しないといけませんか?
遺留分は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなります。
当事務所に関するQ&A
すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。
弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。
杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。
特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。
これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。
また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。
岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。
すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?
原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。
また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。
弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?
弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。
弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。
すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?
電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。
そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。
メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
相続問題のコラム
岐阜県内で約20年間、相続問題(遺留分、遺産分割、相続放棄など)に努めてきた弁護士杉島健二が、相続問題の法律問題について、わかりやすく解説します。
〇 相続放棄について、わかりやすい解説 → こちらから。
〇 遺留分とは何ですか? 遺言書で自分の取り分が少ないときは、どうすればよいですか? → こちらから。
〇 遺産分割について、分かりやすい解説 → こちらから。
〇 無効な遺言書を、有効にできませんか? → こちらから。
相続問題の解決事例
岐阜の弁護士杉島健二が、実際に担当してきた相続問題の解決事例を、ご紹介します。
〇 疎遠となっていた高齢の母の相続放棄 岐阜県各務原市 / 30代 女性 → こちらから。
〇 母が亡くなってから3カ月経過後に母の債権者から約900万円を請求された場合に、家庭裁判所に相続放棄が受理された事案 岐阜県岐阜市 / 50代 / 女性 → こちらから。
〇 遺留分減額請求の調停で、解決金2200万円を獲得 岐阜県岐阜市 / 60代 / 男性 → こちらから。
〇 長女に遺産の多くを残す公正証書遺言について、長女が妹たちに遺留分の額に若干の上乗せをした金銭を支払い、約5カ月でスピード解決した事例 岐阜県岐阜市 / 60代 / 女性 → こちらから。
〇 遺産分割調停で申立人が約2000万円の寄与分を主張してきたところ、その額を約250万円まで減額して調停が成立した事案 岐阜県本巣市 / 40代 / 男性 → こちらから。
〇 亡母が取得した火災保険金約3800万円を兄が管理して弟に渡さなかったため、弟が兄を被告として保険金の半額を請求する民事訴訟を提起した事案 岐阜県大垣市 / 50代 / 男性 → こちらから。
この記事を書いたヒト ー 岐阜の弁護士・杉島健二
経歴
昭和45年5月 岐阜県岐阜市に生まれる
平成16年11月 旧司法試験合格
平成18年10月 司法研修所での司法修習終了
弁護士登録(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)
河合良房法律事務所に勤務
平成22年2月 河合良房法律事務所を退所
岐阜市内にみその町法律事務所を設立
平成25年7月 事務所名を、すぎしま法律事務所に変更
現在に至る
弁護士としての活動
約20年にわたり、交通事故の被害者救済、相続事件を中心に、地元の岐阜県に密着した弁護士活動を展開。
薬害や障害者問題の弁護団にも所属。障害者問題や成年後見人にも取り組む。
趣味
読書、旅行、登山。
2年前には、アメリカ大陸を単独で車で横断しました。
現在は、四国八十八カ所のお遍路に挑戦中(区切り打ち)
 杉 島
杉 島